この連載では、2択形式で「あなたならどっち(を選ぶ)?」と問いかけます。その答えから導き出されるのは、健康を維持するために必要な情報です。選択を間違えたときは、思い込みをアップデートするチャンス! 何気なく続けてきた今までの習慣を見直して、健康習慣を始めましょう。
第2回たばこ
たばこは吸う本人だけでなく周囲の人の健康も害します。
今日から、「ノンスモーカー宣言!」しませんか。
Q吸いすぎなければ大丈夫?
1日3本だけならOK!
吸えば健康を害する
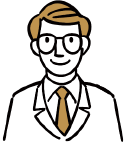
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。
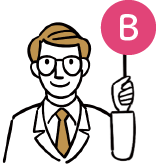
- 答え
B 吸えば健康を害する -
日本人の死につながる生活習慣の第1位であるたばこは、健康に悪影響をおよぼします。
また、新型たばこ(加熱式たばこ、電子たばこ)についても日本呼吸器学会は、「健康への悪影響」を示唆し、喫煙者と受動喫煙者の両方に推奨できないとしています。
たばこが引き起こすさまざまな健康障害
- がん
- 脳卒中
- 結核
- 心臓病
- 糖尿病
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 歯周病
- 流・早産、低体重児出産
- など
広がるたばこの害
吸わない人がたばこの煙(呼出煙※1・副流煙)にさらされることを「受動喫煙」といいます。とくにたばこから立ち上がる副流煙には多くの有害物質が含まれ、日本では受動喫煙で年間約1万5千人※2が亡くなっています。さらに、たばこの有害物質が喫煙者の毛髪や衣類、部屋にあるカーテンやソファ、カーペットなどに付着し、そこから空気中に再拡散される「三次喫煙」(サードハンド・スモーク)による健康障害も問題になっています。
※1 喫煙者が吸って吐き出した煙
※2 厚生労働省 e-ヘルスネット「喫煙による健康影響」より

※3 喫煙者が口から直接吸い込む煙
Q 今さら禁煙しても遅い?
禁煙の効果はすぐに現れるから遅くない
長年の喫煙習慣があるなら、もう遅い
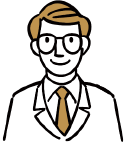
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。

- 答え
A 禁煙の効果はすぐに現れるから遅くない -
禁煙を始めると、直後から体は回復に向かいます。禁煙はいつから始めても遅くありません。
ただし、肺の機能が損なわれていると、完全に回復することが難しい場合があります。
禁煙による健康効果
- 直後
- 周囲の人をたばこの煙で汚染する心配がなくなる。
- 20分後
- 血圧と脈拍が正常値まで下がる。手足の温度が上がる。
- 8時間後
- 血中の一酸化炭素濃度が下がる。血中の酸素濃度が上がる。
- 24時間後
- 心臓発作の危険性が少なくなる。
- 数日後
- 味覚や嗅覚が改善する。歩行が楽になる。
- 2週間~3か月後
- 心臓や血管など、循環機能が改善する。
- 1~9か月後
- せきや喘鳴が改善する。スタミナが戻る。
気道の自浄作用が改善し、感染を起こしにくくなる。
- 1年後
- 軽度・中等度の慢性閉塞性肺疾患のある人の肺機能の改善がみられる。
- 2~4年後
- 虚血性心疾患のリスクが、喫煙を続けた場合に比べて35%減少する。脳梗塞のリスクも顕著に低下する。
- 5~9年後
- 肺がんのリスクが喫煙を続けた場合に比べて明らかに低下する。
- 10~15年後
- さまざまな病気にかかるリスクが非喫煙者のレベルまで近づく。
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の効果」より
Q禁煙外来って、どんなところ?
たばこで健康を害した人が行くところ
たばこをやめたい人が行くところ
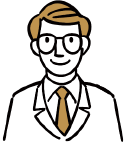
上記で、あなたが正解だと思う答えを選択してください。
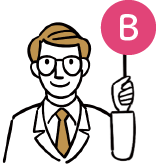
- 答え
B たばこをやめたい人が行くところ -
たばこはニコチン依存症と習慣により、やめるのが難しい場合があります。1人で耐えるのがつらいときは、禁煙仲間を作るなどの方法もあります。
禁煙外来でお医者さんと禁煙に取り組めば、より楽に確実に禁煙できます。
- 自分に合った禁煙方法を見つけよう
-
- 吸いたくなったら気を紛らわせる
- ・水を飲む、ガムをかむ ・深呼吸をする ・体を動かす ・歯をみがく
- 禁煙仲間を作る
- 周囲で見つけたり、インターネットなどで見つけたりする
- 禁煙外来に行く
- 禁煙成功率が、自力に比べて4~6倍高まる※
- ※厚生労働省「スマート・ライフ・プロジェクト」より
 全国禁煙外来・日本禁煙学会
http://www.nosmoke55.jp/nicotine/clinic.html
全国禁煙外来・日本禁煙学会
http://www.nosmoke55.jp/nicotine/clinic.html
全国禁煙外来・禁煙クリニック一覧(日本禁煙学会)
 健診結果の読み方生かし方
健診結果の読み方生かし方
生活習慣病の特徴は、自覚症状がないまま静かに進行していくことです。症状としてあらわれるときには、取り返しがつかないところまで悪化していることもあります。健診結果から、将来のあなたの姿を予測することができます。健診結果を活かし、生活習慣病を予防しましょう!
「貧血」に関する検査項目と基準範囲
[赤血球数(RBC)]
男性 432~528×104/µL 女性 387~478×104/µL
[血色素(ヘモグロビン<Hb>)]
男性 13.1~16.3g/dL 女性 12.1~14.5g/dL
[ヘマトクリット(Ht)]
男性 40.8~47.9% 女性 36.3~43.3%
全身へ酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンが減少し、体内が酸欠になる病気が貧血です。特に多いのがダイエットや偏食で鉄分が不足して起こる「鉄欠乏性貧血」です。
貧血を防ぐおすすめライフスタイル
- 鉄分を多く含む食品※を食べましょう
- 栄養バランスに気をつけましょう
- たんぱく質、ビタミンCをとりましょう
- ※レバー(豚・鶏・牛)、貝類(しじみ・カキなど)、納豆、ホウレンソウなど
参考資料『健診結果の読み方・生かし方』監修:奈良信雄 順天堂大学 客員教授 東京法規出版刊
